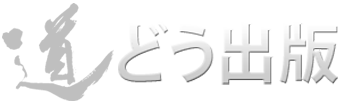2012年9月2日(日) 横浜市 神奈川県民ホール 主催 どう出版



宇城師範が「やってみせる」だけでなく、宇城師範が会場全体に「気」を送ることにより来場者全員が一斉に行なう「不可が可になる体験」には、理屈なき驚きとともに歓声が上がっていました。
「人間の持っている無限の可能性に驚かされました。」
「『百聞は一見にしかず』です。感動の一言です。」
「気の体験をして、普段自分は気が抜けていることに気づかされました。」
「人間の身体はこんなにも強いんだと感じました。」
その驚きは、自身に眠る人間本来の潜在能力への感動、さらには生かされていることへの畏敬の念につながります。同時に湧く「なぜ自分ではできないのか」という疑問に対する「答え」が随所で実践・検証されていきました。
〈第一部〉 統一体の解説・実演
第一部は『コロラド合気道合宿指導の記録』の映像上映から始まりました。 米国コロラド州 ロッキー山脈のふもと標高2500メートルの高地で毎年行なわれている合気道合宿は、全世界より主に合気道指導者250余名が集まる大規模な1週間の合宿です。宇城師範は唯一合気道以外のスペシャルゲスト・インストラクターとして毎年招かれ、指導しました。合気道以上に合気を使いこなしていると言われた様子が見事にスクリーンに写し出されていました。 〈 放映DVDの詳細 〉
その後パワーポイントを使い、「気」が生まれるプロセスとして「生と死のある日常をいかに真剣に生きるか」という姿勢や、人間本来のあり方「統一体」についての詳細が語られました。

たとえば同じ100mを泳ぐにしても、水平に泳ぐか垂直に潜るかで、その本質は大きく変わります。
「(A)水泳=競技=スポーツ」と、「(B)潜水=生と死が日常に関わっている=武術」。
(A)はあくまでも競技であるが、(B)は生と死に直結する厳しさがある。すなわち前者は「競争・勝ちたい」という欲、後者は「感謝・祈り・畏怖の念」が導き出され、生き方にもそれは大きく影響してくることの違いがあります。
「江戸時代には侍が日常的に刀を差していました。
刀を抜いたらどちらかが殺されるわけです。常に生と死がかかっていた。
だから「斬れる刀を抜かない」「戦わずして勝つ」という境地が生まれた。」
その武術修行のプロセスとしてある「事理一致」の説明がされました。
「 「事」とは、事実、所作(手足の動き)、技・術。
「理」とは、理合・真理、目に見えない自然の法則、心の働き
事理が一致してはじめて、右手と左手が合わさってはじめて音が出るように、
気の一端が生まれるのです。」
●太ももに乗られても痛くない・・・
ステージに仰向けになった男女数人の太ももに、順番に宇城師範が乗っていきます。
男性は痛がって乗れる状態ではないが、女性は痛がることなく宇城師範がさっと乗ります。・・・
この事実は常識からすると矛盾ですが、まさに気の力を示すものです。
| 1.足をかけられただけで痛い | 2.乗られても平然とする女性 |
 |
 |
人間の身体は、想像を絶する神秘に満ちていること、また「身体は心に、心は身体に」強く支配されていることなど、気により、人間の潜在能力の存在の数々を実演で示されました。

気を通され、腕が一瞬にして強くなる。人を乗せたまま、左右に移動することも可能
第二部は、宇城空手の真髄の披露から始まりました。
相手の攻撃に対し真っすぐに入り、投げる ――
それを可能にする方法も様々に、姿勢をつくる、中心をずらす、残心、そして気による実演が示されました。
講演会中に行なわれた数々の実演検証において宇城師範は終始、「絶対にヤラセや、相手の協力が得られない」状況をつくってから行ないました。このことで来場者は目の前で起こる「不可が可になる」通常ではあり得ない事象も深い納得をもって受け入れていきます。
●メリケンサックを相手の組手
組手の場合は、攻撃の拳にメリケンサック(鉄製の武器)をはめさせて、当たればただの怪我では済まない状況で行なわれました。
メリケンサックの攻撃に対しては、打ち合ったり組み合ったりというスポーツ的な対処では相手を制することはおろか、向かっていくことさえできません。間を制し、相手を無力化するなど武術的な「できる」があってはじめて、相手に入り制することができるのです。




メリケンサックをはめた相手との組手(攻撃はフルコン無差別級世界チャンピオン)
●無力化・ゼロ化
1.がっちり組んだ5人を、簡単に無力化し動かす


2.男性がいくら引いてもびくともしないが・・・

3.女性でも、「気を通される」と簡単に動かすことができる

●「人間力」
ステージに来場者40人ほどが上がって2つの集団がつくられました。左に体重75キロ以上の人の集団。右はそれ以下の体重の人の集団。互いに体が触れる程度で立っているだけです。ここでいくつかの事象が示されました。
ひとつが、集団で生まれる「人間力」。
正面から力いっぱい押されても、がんばって耐えているわけでもないのにまったく崩れません。

さらに、
○ 大きい集団より小さい集団のほうが強いこと
○ 集団の中の一人でも他のことを考えると、全体が弱くなること
最後には、来場者で最年少の女の子(6歳)がお母さんとともにステージにあがりました。大人の男性がいくら押しても崩れない、ましてお母さん1人で押したのではびくともしない集団を、女の子がお母さんに触れて応援することでその集団全体を見事に崩しました。宇城師範の著書『子どもにできて大人にできないこと』で紹介された子供の力を実際に目の当たりにした来場者から、自然と拍手が沸き起こりました。
1.お母さんが押すが集団はびくともしない

2.子供がお母さんに触れただけで、集団が崩れだす


「子供は衝突する心がないので押すことができるのです。
子供の自然体の調和力によって、子供が触れるだけで
大人はそのエネルギーをもらうことができる。」
≪動画でご覧ください≫
成人男性と、お母さん&女の子が、それぞれ集団を押す様子です。
一人が四つん這いになり、その上にもう一人が四つん這いの状態で乗ります。
下の人は片手を上げられない状態です。そこに下の人の腹の下を子供がくぐります。すると瞬時にして下の人は手が容易に上がるようになります。これが「守る」という人間にもともと備わった無意識の人間力です。
しかし、頭で意識的に「守ろう」とすると今度は逆に手を上げられなくなります。
1.手を上げられない

2.子供がくぐると楽に手を上げられる

3.意識して「守ろう」とすると、とたんに弱くなる

4.宇城師範に「気」を通してもらう。一番楽に手を上げられる

さらに、子供がくぐった時の下の人の身体変化は、下の本人よりも上に乗った人のほうが、よりはっきりと感知します。「自分が変われば、周りが変わる」の一例です。
● 気は連鎖する
気は次々と連鎖し、周りを取り込んでいくことも示されました。
| 1.宇城師範が杖で投げる | 2.投げられた人の足を掴むと・・・ |
 |
 |
| 3.投げられる | 4.投げられた人の足を掴むと… |
 |
 |
|
5.投げられる・・・ 気の連鎖は延々と続く |
|
 |
宇城師範が杖を掴む一人を投げます。投げられた人の手や足をもう一人が掴みます。すると投げられた人はやすやすと掴んでいる人を投げてしまいます。投げられた人は「やられた」と思いがちですが、気で無力化されて投げられた人は気が通った状態にあるので、投げられたにもかかわらず、このように掴んでくる人を簡単に投げることができるのです。この気の通った状態は投げによって延々と連鎖していきます。
「投げられたけれど、身体は強くなっている。すなわち相手にエネルギーを与えている」
優劣を超えた次元に“調和”の世界があることが、実際に示されました。これは、まさに「絆」とも言えます。

相手をおんぶした状態で体を左右にまわす。気を送られるとおんぶした人と一体となり、まったくぶれなくなる

気を送られることで、上の人が重くなったり、軽くなったり変化する
体重は変わるはずがないのに、重たくなったり、軽くなったりするというのは常識ではあり得ない世界です。・・・ しかし「気」はそれを可能にするのです。
●無力化
3人が杖をしっかり掴み、さらにそれを2人ががっちり支える。
パワーのありそうな男性が倒そうと試みてもびくともしなかったのに、計5人を片手で投げる宇城師範。



サンチンの型が披露されると、宇城師範の動き・呼吸に来場者全員が集中し、場内は張り詰めるほどの静けさに包まれました。
「型から技が生まれるのではないです。
型の中に心を取り込んでいって、
自分のもの〈形〉にすることが大事です。」
まさに
「型は美しく技は心で」
「心豊かなれば技冴ゆる」 です。

サンチンの型演武


サンチンによる無力化
気が通ることで得られる、筋トレでは絶対に得られない力が徹底的に示されました。
1.中央の一列に気を通し強くする。来場者が腕にぶら下がって確認する

2.そのまま一列を押し込む宇城師範

3.手を放しても列の勢いは止まらず・・・

4.壁にぶつかるまで下がりつづけた

宇城師範が示した、身体に気が通ることで瞬時に強くなるということ。これは筋トレという「鍛え方」に大きな疑問を投げかけます。
「人間の叡智。それは心、思いやり、やさしさ、そして人を幸せにすること。
人を幸せにしているということが、成長しているということです。
点のような卵子からわずか10ヵ月で人間になる。
そういう神秘の上に、私たちは生かされている。
生かされている間に、人のため世の中のためにつくすことだと思います。
争いがだめなことは誰もがわかっています。
それをただ「反対 反対」と唱えるのではなく、今ここで示したように
相手と調和することが平和への第一歩ではないかと思います。
そして調和するためには、まず自分の心を開くこと。
今日を機に、そういう方向に向かっていただけたらいいなと思います。」
宇城師範が示した圧倒的な武術の技と、「気と実践」によって示される絶対仮説と理論、そして「人間力」。さらに宇城師範に気を通してもらうことで来場者全員が自らの「人間力」を体験したことは、生かされている喜びと感謝の思いを湧き上がらせました。わずか3時間の講演で、来場者の皆さんの目が希望に満ちあふれていく様子そのものが、日本の希望であるのかも知れません。
来場者の感想からも、希望に心躍らせる様子が伝わってきます。
こちらからお読みください。 ⇒ 来場者の感想


休憩時間、講演会終了後に行なわれたサイン会では、順番待ちの列でロビーがいっぱいになった
| ■ リンク・ブログ関連記事 道塾 宇城憲治塾長コラム 宇城師範が講演会を終えての所感を書いています。 宇城道塾事務局ブログ |