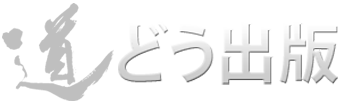季刊『道』連載 岩井喜代仁氏「今日一日を生きる」より
季刊『道』より、薬物依存回復施設・茨城ダルク代表 岩井喜代仁氏の連載記事「今日一日を生きる」を紹介いたします。
覚せい剤や大麻だけでなく、脱法ハーブ、脱法ドラッグ、そして市販薬、処方薬……日本でも容易に薬物乱用に陥る環境になりつつあります。
さらに、薬物乱用が引き金と思われる事件が頻発するようになり、もはや薬物問題はいつ我が身に降りかかってもおかしくない身近な社会問題です。
20年にわたって薬物依存症者の回復と、彼らの社会復帰への取り組みを行なってきた岩井氏に、「薬物問題の今」を語っていただいています。
(2012年6月10日、大阪市心斎橋の路上で男女2名が通り魔に刺され死亡する事件が起きた。
刺したのは、覚せい剤取締法違反で服役し、出所したばかりの男。
犯行動機として出所後の生活不安をあげ、「人を殺して死刑になろうと思った」と語った。
事件当日は覚せい剤の使用は認められなかったが、
過去に同違反により少なくとも2回は服役したという。)
私にしたらあれはもう合併症ですよ。完全に薬物依存症以外の病気も発症しています。おそらく刑務所内でも処方薬(向精神薬)を飲んでいたと思います。しかしそこで私たちダルクが「あの子は病気だよ」という話をすると、社会的に一般の人から見たら「薬を使ったやつが悪い」「それは自分たちの正当化じゃないですか」という話になる。
だけど、覚せい剤を使わなくてもアルコールを飲んで、そこにフラッシュバック(過去の薬物使用による症状の再燃)が起きることもあるんです。
心斎橋の事件の犯人も出所直後に一度は薬物支援施設につながりながら、自分の意志でそこを出て大阪で事件を起こした。私たち施設の人間には「出て行く」という人を止めることはできないんです。
今、「刑の一部執行猶予制度」という法律が制定されようとしています。今回の事件は、この法律があったら防げたのです。それは、この法律が薬物事犯の出所者はいやでも回復施設に行かなければならないと定めるものだからです。しかしこの法案は参議院は通りましたが、まだ衆議院を通過していません。国会があんなにもたもたとしていたら当然でしょう。――
家庭・施設・刑務所を際限なくめぐる薬物依存症者を、周りにも本人にもいい状態で社会に戻そうと奮闘する、ダルクの記録です。
全文は、最新号『道』174号でお読みください。
ダルクとは
覚せい剤、有機溶剤(シンナー)、市販薬、その他の薬物から解放されるためのプログラムを持つ民間の薬物依存症リハビリ施設。