〈2013年3月18日発売〉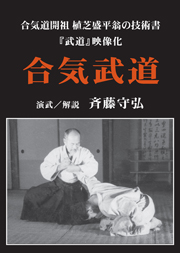 合気道開祖 植芝盛平翁の技術書『武道』を斉藤守弘合気道九段が解説・演武する『合気武道』がDVD版として再登場!
合気道開祖 植芝盛平翁の技術書『武道』を斉藤守弘合気道九段が解説・演武する『合気武道』がDVD版として再登場!
ビデオ版のため長く絶版となっておりましたが、多くのご要望にお応えし、このたびDVDとしてお届けすることになりました。
合気道初期の技を、開祖とともに暮らし薫陶を受けた斉藤守弘師範がていねいに再現。
合気道のより深い理解に導く、貴重な資料です。
合気道開祖 植芝盛平の技術書『武道』映像化
DVD 合気武道
演武・解説 斉藤守弘
『武道』は、昭和13年(1938)に合気道開祖植芝盛平翁が出版した唯一の技術書です。合気道技が現代に変化発展していく様を理解する重要な鍵を与えてくれるとともに、開祖自身による演武・解説した唯一の技術書としても非常に貴重なものです。
 本DVDでは、開祖の下で24年間薫陶を受けた斉藤守弘合気道九段が、この『武道』に収められた50の技の解説を読み上げ、一つひとつ再現しています(1986年撮影)。
本DVDでは、開祖の下で24年間薫陶を受けた斉藤守弘合気道九段が、この『武道』に収められた50の技の解説を読み上げ、一つひとつ再現しています(1986年撮影)。
『武道』をより深く味わっていただくため、付録として技法図解・解説の(一)~(六)の複製をパッケージに封入しました。(B6判4ページ)
《収録内容》
片手取り入身投げ・呼吸投げ/正面打ち一教・二教・三教・呼吸投げ・小手返し/横面打ち入身投げ・四方投げ・二教・四教・五教/両手取り四方投げ・天地投げ/突き入身投げ/後襟取り呼吸投げ・固め技/後両手取り呼吸投げ/太刀取り小手返し・呼吸投げ/短剣取り/剣対剣/銃剣/槍取り/座り技呼吸法/ほか
収録時間: 42分
定価: 5,250円(税込)
ご注文はこちらです ⇒ [購入ページ]
『武道』について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1930年代の開祖の弟子には宗教界、実業界、政界、軍部からのそうそうたる人物が名を連ねていました。『武道』は1938年に開祖によって、開祖の弟子であり軍部高官である賀陽(かや)の宮のために編纂された教本です。これは開祖が陸軍戸山学校で定期的に指導していたことによるものです。賀陽の宮はのちの1942年、開祖が教鞭をとった戸山学校の校長に迎えられています。
また開祖は1930年代後半、様々な古流武術の武器技、なかでも鹿島新当流を合気道稽古のなかに取り入れて研究を重ねています。『武道』に収められた50の技のうち、まさに3分の1は、小刀、剣、槍、銃剣など、武器を使用した技で占められています。
『武道』は一連の技を開祖自身が演武・解説している唯一の資料であり、歴史的にも非常に貴重なものと言えましょう。
斉藤守弘 合気道九段 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1928年~2002年 開祖亡きあと茨城道場長を務める。
1942年戦時中に、茨城県岩間に引退した開祖は、農作業と瞑想、そして合気道修行に日々を過ごしていました。戦争終結後の1946年、若き日の斉藤守弘師範が開祖の岩間道場に入門しました。日本国有鉄道に勤務する斉藤青年は、職場が交代制をとっていたことが幸いして開祖のもとで直々の稽古を長い年月にわたって受けることができました。斉藤師範が開祖のもとで過ごした期間は通算24年に及びます。この間、斉藤師範は家族とともに植芝家に仕えました。
斉藤守弘師範は、武器技を含む開祖の合気道を教授するために海外にも精力的に出かけ講習会を行ないました。その際、斉藤師範は合気道技の源を示す資料として教本『武道』の重要性を強調し、講習会で『武道』をしばしば参照しています。
「この『武道』の技の再現によって開祖の技の歴史がよく理解されることでしょう。
開祖は晩年、「合気道の完成は戦争後にある」と言われていましたが、なるほど、この戦前の『武道』の技と開祖晩年の技とを比較すると大きな開きがあります。なぜこの技が晩年の技の形に改良されたのか、比較してみるとよくその理由がわかります。その意味で今後の合気道の研究のためにも、いかにこの『武道』が重要であるかがおわかりになると思います。」 ――斉藤守弘師範談(1986年)
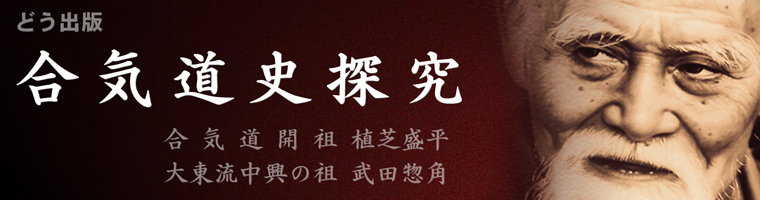

 「あの世はいいところ。
「あの世はいいところ。
